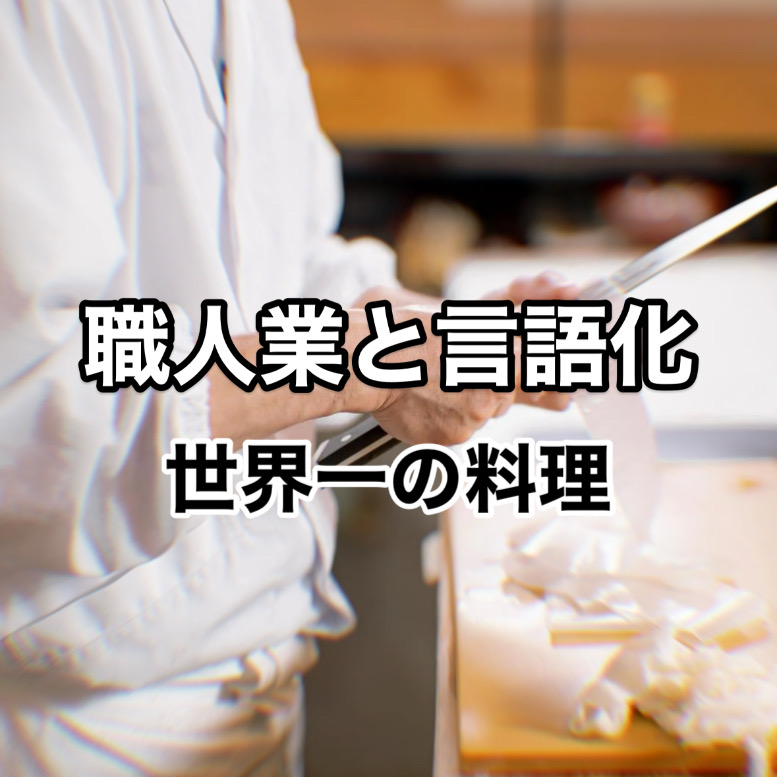◯飲食店の教育◯
飲食店で働いているスタッフが、誇り高く働けない要因は「教育」であると問題提起した。
日本の飲食店は、日本料理をはじめ、他の料理ジャンルにもいる“職人”が発展させてきたという経緯がある。飲食店の職人は、ひとつひとつの食材や素材の個体差を見分け、それに合わせて“感覚”と長い間に培った“経験”でお客様が満足する料理を完成させれる。これは、本当に素晴らしいことだと思うし、この職人のおかげで日本料理は世界一と呼ばれるまで成長したのは間違いない。職人は厨房だけでなく、バーテンダーやバリスタ、パティシエ、ソムリエなどの職種にも存在する。また、調理する側ではないので、あまり職人として表現されることはないが“ウエイター”と呼ばれる接客のプロの方々にも職人レベルにその技術や考え方にこだわりを持っている方々もいる。
調理にしても接客にしても、飲食店では食材の鮮度、食材の火の入り方、それに季節、気温、湿度など、またそのお客様に合ったものなど、細かな目線で相手のニーズを判断して、感覚と経験を持ってして調理、接客を普段から行なっている。なので、同じことが毎日起こるわけでなくその場その場で対応しなくてはならないことが日常に溢れている。ベテランになればなるほど、この対応が当たり前になり、頭で考えずにひとつひとつ対応するようになってくる。これを調理、接客問わず“職人業”だと思う。
その中で、昨今、クックパッドのようなレシピの公開、冷凍技術発展による冷凍食品の発展によって、職人業を必要としない環境が一部ある。職人ほど美味しいものが食べられないにしても、それに近しいものを味わえるようになっているこの時代。また、Z世代をはじめとするインターネット環境が当たり前にある世代からすると、何かの教育をされる時に、“感覚”や“経験”で語られると理解することがなかなか困難であり、その業界で働こう、頑張ろうというモチベーションには繋がらないことがある。その原因としては、職人がひとつひとつ違う食材や、ニーズがひとりひとり違うお客様において、対応してきた職人業を「言語化」することができなかったことにあると考えます。
職人たちの昔ながらのセリフで「俺の背中を見て育て」がある。実際に、私も昔言われたことがあります(笑)もちろん師匠や先輩たちの背中を見て学ぶことが多いものの、何も言語化されずに成長しろと言われてしまうと、そのお店で成長できる人は相当限られると思う。勘のいい人、観察力がある人、その先輩と人間関係ができてる人、経験のある人、など結構限定されてしまう。この少子高齢化の中で、その環境が続いていければ、人手不足になるのは必然である。しかし、調理する職人業や、接客する際のホスピタリティやセリフを言語化してマニュアルに落とし込むことなど可能なのか?マニュアル化するならファストフード、マニュアル化できないレベルのものは先輩からの指導。このような区分けがなされているのが現状ではあるが、私はこのマニュアル化を業界全体で取り組むべきだと思っている。これは飲食業界全体の課題だと考える。その会社、その会社ごとにマニュアルは存在するのだが、業界全体をまとめている労働組合のようなものがない飲食業界では、このマニュアルやそれぞれのノウハウなどが共有されることがほとんどないのが現状だ。
店舗の業態にもよるのだろうが「マニュアル7:背中3」くらいの割合で、構成されるべきだと私は考えます。そのために、私が25年間で培ったものを少しずつ言語化していこうと思う。職人業が7割言語化されて、そのマニュアルを読み込んが方々が現場で先輩の背中を見て残りの3割を学んでいくことができれば、もっと楽しく誇りを持って飲食店で働ける環境が少しでもできると思う。